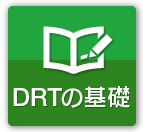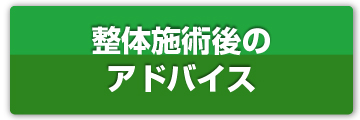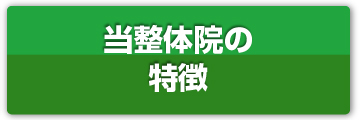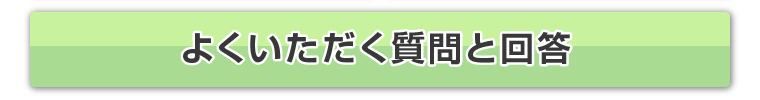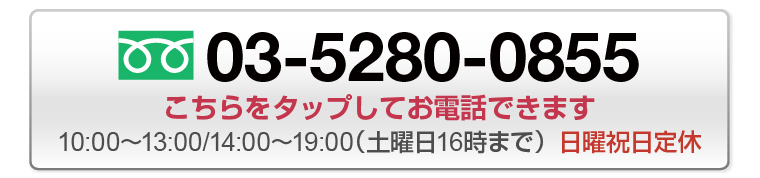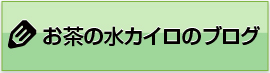- ここで今までの検査を整理します。思い出して下さい。
- まず下肢の抑圧検査で身体が大きく右と左のどちらに傾いているかを調べます。
骨盤の傾き、脊柱の傾き、ストレスポイントの辺りをつけます。 - スプリング検査、脊柱起立筋の検査で後方変位を調べます。
- 僧帽筋検査でメジャーである上部胸椎がどっちに側方変位しているか調べます。
- 頭方からの脊柱検査、脊柱ローリング検査でどの椎骨の可動性が無いかを調べます。
具体的にアジャストする椎骨を調べていきます。 - 腹圧の検査=脊柱の前後のバランスを調べます。
具体的には上部胸椎の後方変位のアジャストメントが強く必要かどうかを調べます。
- 脊柱の大きな変位を治療するのが目的です。
DRTでは原則として右からか左からかのTL方向からしかアジャスしません。
これは他のテクニックには見られない。ユニークな特徴ですが臨床的にはこの方が効果的です。
繰り返しになりますが大きく右に傾いているか左に傾いているか
もしくは正中線から右に側方変位しているか左に側方変位しているかを治療するのです。 - 上記の検査を例にしてどのようにアジャストするのか考えてみます。
- 下肢の押圧検査で左足が可動性あり。骨盤が左上方に傾き、脊柱は右凸になっている。
つまり大きく左に傾いているかもしれないと言うことです。
そして中部胸椎で右への大きな動きがありました。 - スプリング検査、脊柱起立筋の検査で中部胸椎~上部胸椎に後方変位を検出。
- 僧帽筋検査で右に硬結と圧痛あり。上部胸椎の右側方変位の可能性あり。
下肢の押圧検査の結果と併せて考えても右からのアジャストになりそうだとアタリがつきます。 - 頭方からの脊柱検査、脊柱ローリング検査でD1、D5、L1、骨盤の右回旋を検出する。(骨盤については後述)
- 腹圧の検査で圧痛あり。D1の後方変位が強い。
以上のようになります。これらの検査を総合してアジャストしていきます。